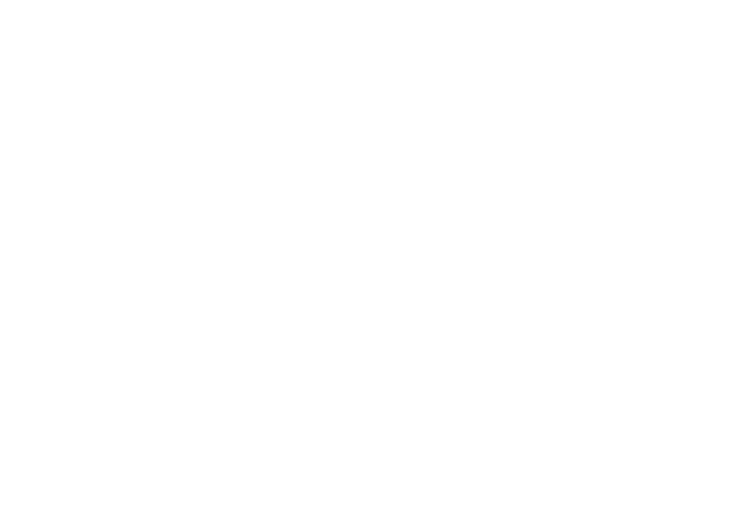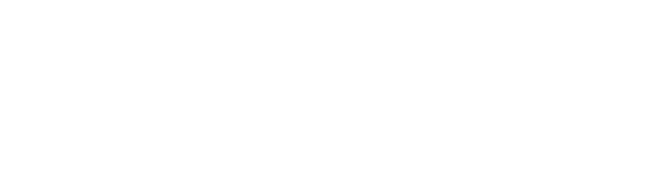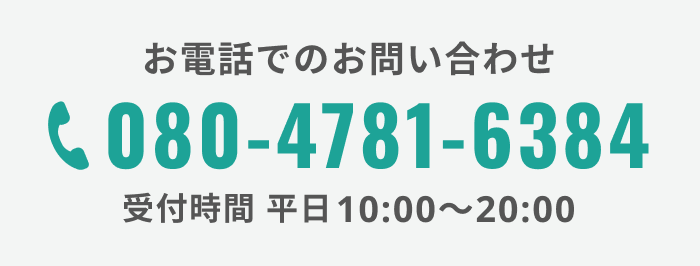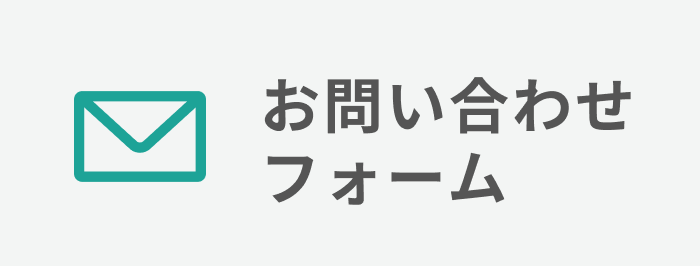Q
法律事務所のホームページ制作(リニューアル)を検討中ですが、失敗しないためにはどうすればいいですか?
A

プロジェクトの責任者としての意識を持ち、必要最低限の知識を備えることが重要です。


「プロジェクトの責任者」として判断する姿勢が成功の鍵
弁護士の先生方に「なぜホームページを作ったのか?」とお聞きすると、
- 「開業時に紹介された業者にそのまま任せた」
- 「業者が“法律に強い”と言っていたから」
といった回答が多く見られます。
しかし、ホームページ制作会社には様々なタイプがあります。
- 法律専門を謳いながらテンプレート中心の会社
- 見た目重視で導線設計やSEOに弱い会社
- 数年前の制作手法をそのまま踏襲している会社など
最近では、離婚・相続・債務整理などの分野に特化した競合事務所も増えており、ホームページの内容や導線が、集客や売上に直結する時代となっています。
だからこそ、ホームページを新たに作成・リニューアルする際には、 弁護士自身や担当者が「プロジェクトの責任者」として、方向性や内容を主体的に判断する姿勢が不可欠です。
ホームページの役割と、依頼者の検索行動の変化
かつて法律事務所のホームページは、「事務所名で検索し、アクセス方法や電話番号を確認する」といった用途が中心でした。
しかし今では、ユーザーは以下のような検索行動を取るようになっています:
- 「地域名+離婚弁護士」など、エリアと専門分野の掛け合わせ
- 「慰謝料 請求方法」や「相続 もめた場合」など、具体的な問題提起型の検索
- 「法律相談 不安 誰に相談すればよいか」など、心理的ハードルを伴う検索
このように、ユーザーが抱える不安や状況に寄り添ったコンテンツと導線設計が求められる時代です。
ホームページに掲載するべき情報も、以下のように広がっています:
- 弁護士の経歴・資格
- 扱う分野の具体的な事例
- 初回相談の流れ
- よくある質問や対応エリア
- 相談者の声や実績
また、ユーザーの検索動向やニーズは数年単位で変化するため、3〜5年に一度は見直し・改善が必要です。


競合とターゲットの分析がカギ
ホームページ制作の目的は、事務所によって異なります。
- 開業のタイミング
- 古くなったデザインの刷新
- 問い合わせ数の低迷
- 他社と差別化したい
ですが、どの目的であっても“競合との差別化”は避けて通れません。
たとえば、以下のような差別化ポイントは、相談者の判断材料になります。
- 駅チカ・アクセスの良さ
- 女性弁護士が在籍
- 土日・夜間相談可
- 相談件数・実績の豊富さ
- 地域密着の対応力
ただ見た目を刷新するだけでは、効果は限定的です。強みが明確に伝わるサイト構成にすることが重要です。
ターゲット・検索キーワードの把握も不可欠
現在は、地域別・分野別の検索キーワードの母数も簡単に調べられます。たとえば、「市名+弁護士」よりも「駅名+離婚相談」で検索される傾向が強い地域もあります。
こうしたキーワード分析は、ホームページ制作前の戦略設計に必須です。
また、Googleアナリティクスやサーチコンソールといった無料の解析ツールを活用することで、
- どのページが読まれているか
- どのキーワードから流入しているか
- 離脱の多いポイントはどこか
といった改善のヒントを得ることができます。
まとめ|“プロジェクトの責任者”として成功に導くために
ホームページを「ただ作る」のではなく、依頼者に届き、選ばれ、問い合わせにつながる設計にするには、以下のような視点が欠かせません:
- 開業のタイミング
- 問い合わせ数の低迷
- 強みを正しく見せる構成と導線を設計する
- ツールで実際の行動を測定し、改善を続ける
制作会社任せにせず、自らのサービスとブランドをどう届けるかを判断できる「プロジェクトの責任者」としての視点を持つことが、成功の第一歩です。